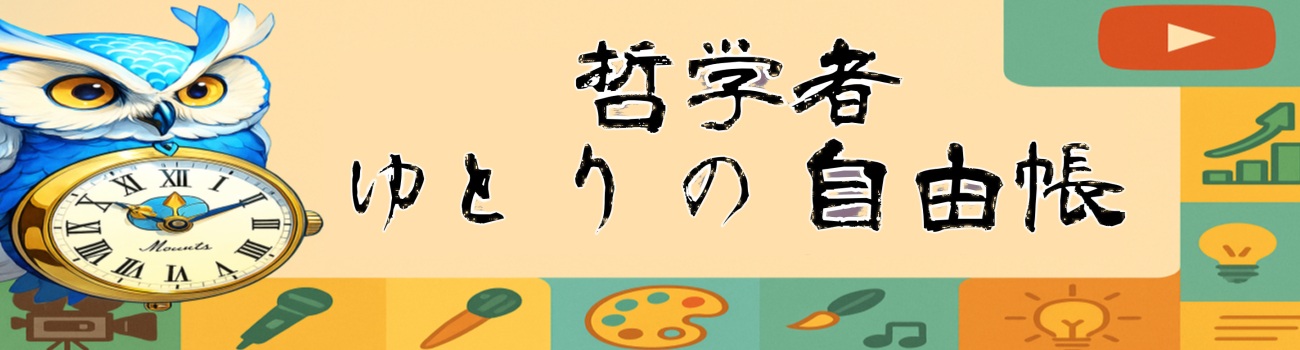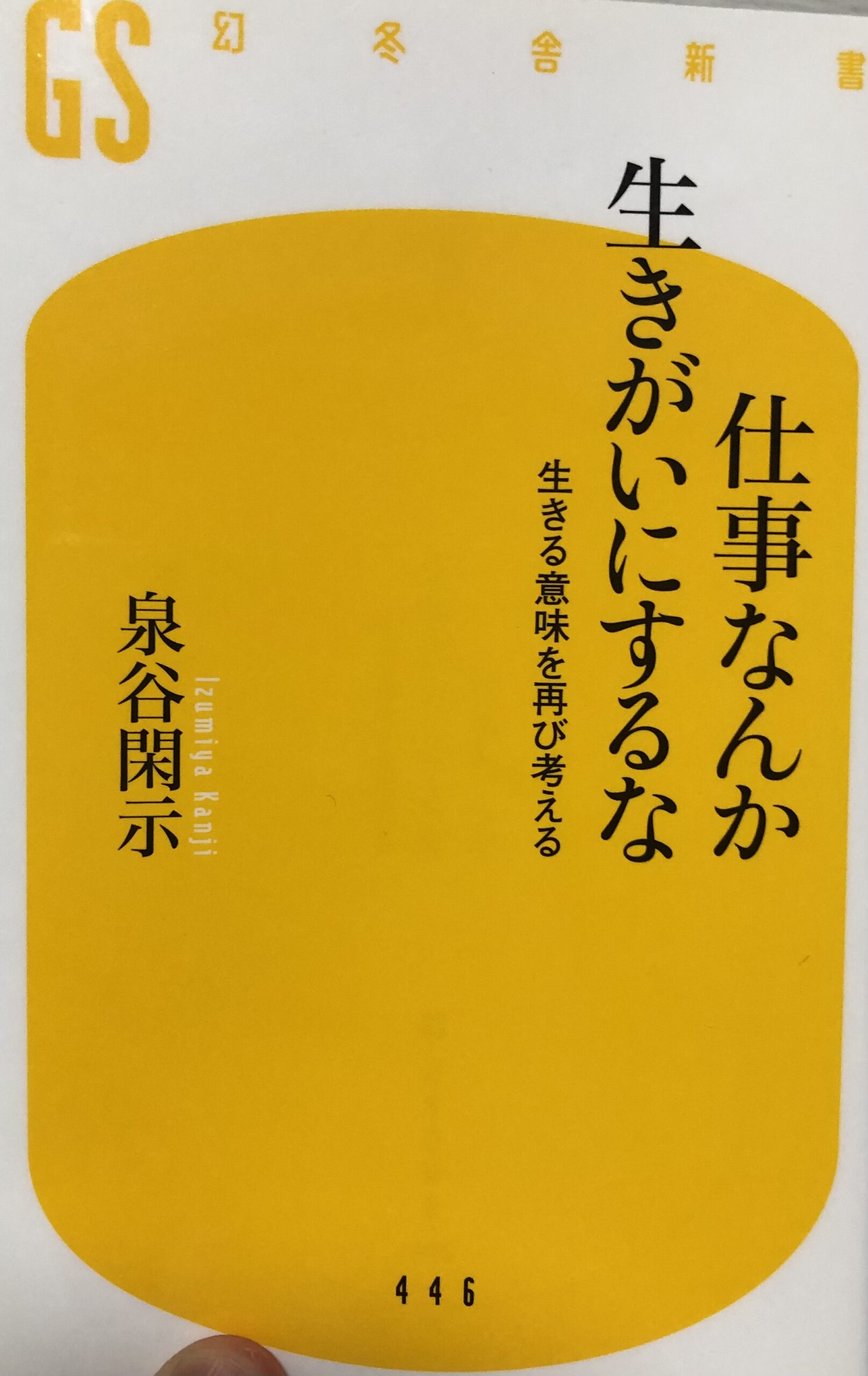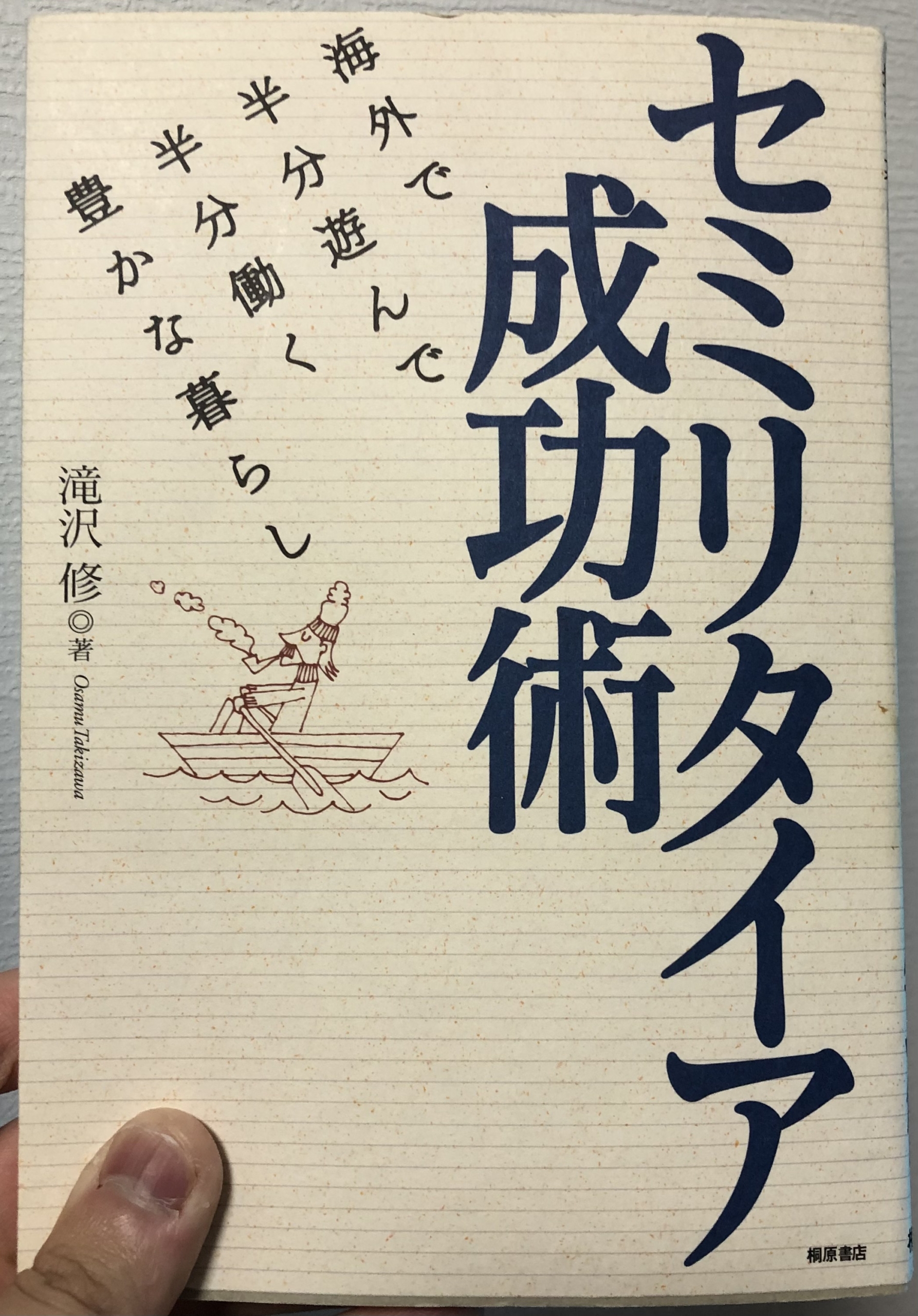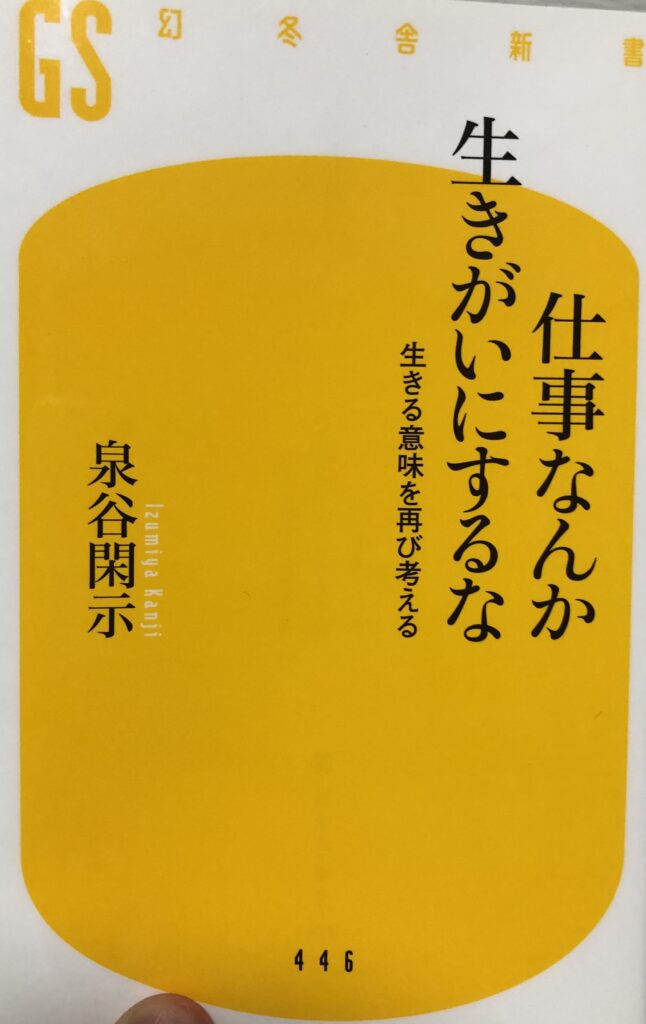
今回ご紹介するのは、泉谷閑次の「仕事なんか生きがいにするな」です。
自分に素直になること、今を楽しむことの重要性に気づかせてくれる書籍でした。
この書籍の内容から、私が興味を持った部分をご紹介させていただきます。
若者の主体性のなさ・恋愛離れ・結婚離れの理由?
「あなたのためよ」という名目の下、親の価値観に縛られて「ノー」を許されない状況で生き抜かなければならない子供たちは、主体性を放棄する以外に生き残る道がありません。
つまり、こうして大切な自我の基本であるはずの「好き/嫌い」というものが封印されてしまうことになります。
このように、自我の芽を摘まれて育ってきた彼らにとっては、精一杯のささやかな希望が「もうこれ以上何かを強制されたくない」という願い、つまり「せめて面倒なことは最小限にして、少しでも楽な人生を送りたい」という形になるのは、必然の結果なのです。
「仕事なんか生きがいにするな」P.23,P.24より抜粋
これは私自身にも当てはまっていて、かなり心に突き刺さりました。
昨今の「お利口さん症候群」や「若者の主体性のなさ」「恋愛・結婚離れ」など様々な問題の原因はこれなのではないでしょうか?
自分に出来ないことは他人もできないと考えてしまう

大抵の親御さんは自分の子供に学校のお勉強を強要し、出来るだけ良い大学に入って、サラリーマンになるように教育します。子供が勉強が好きか、勉強に向いているかは関係ありません。
子供は親に養ってもらう立場なので、「ノー」は許されません。
なぜサラリーマンになるように教育するかというと、「誰かに雇ってもらって労働者として稼ぐ」というお金稼ぎの方法しか知らないからです。悪意はありません。「あなたのため」は噓ではありません。だってこの方法しか知らないんですから・・・
人は自分の身の回りで起きていないことは実現不可能だと考えてしまうので、例えば株式投資で儲けを出したことがない、もしくは周りにそういった人がいないと「株式投資はギャンブル。儲けを出すことが出来るのはごく一部の特別な人間」と考えてしまいます。
同じように「誰かに雇ってもらって労働者として稼ぐ」以外の方法は一部の特別な人間にしかできないと考えてしまうのです。
サラリーマンを目指すのは本当に安全策か?

しかし、サラリーマンを目指すのだって絶対安定という訳ではありません。
雇ってくれる人がいなかったら?
経済状況が悪くなって募集がなくなったら?
経済状況が悪くなって解雇されたら?
雇ってくれた会社が倒産したら?
そもそも会社勤めが絶望的に向いていなかったら?
また、基本的に資本主義社会において労働者が優遇されることなどありえません。だって「資本」主義ですからね。
資本主義社会における階級のピラミッドは一番上から資本家・企業・労働者です。
一番下なんですから優遇される訳がないですね。
実際政府は金融商品にかかる税金や法人税は低く抑えていますが、消費税などの税金はすごいペースで上げています。このことからも資本家や企業は優遇しますが、労働者はないがしろにしていることが伺えます。
なので最初から学校のお勉強をやらせてサラリーマンを目標にするのではなく、子供が勉強が嫌い・向いてない場合はその意思を尊重し、勉強以外の子供の興味を育んであげることが主体性向上に繋がるのではないでしょうか?
「生きる意味」なんてある?
青年期には重要に思えた「社会的」とか「自己」といったものが、必ずしも真の幸せにはつながらない「執着」の一種に過ぎなかったことを知り、一人の人間として「生きる意味」を問い始めるのです。
~中略~
従来は「なりたいものになれるかどうか」「就きたい仕事に就けるか」という内容が多かったのですが、近年では「何がしたいのか分からない」「できれば面倒なことはしたくないが、やらなければならないとしたら何をするか」「なぜ働かなければならないのか」といったものに変化してきているのです。
「仕事なんか生きがいにするな」P.53,P.55より抜粋
ぶっちゃけ「生きる意味」なんてものはないと私は考えています。
生きた証を残したいとかいう意見を目にしたりすることもありますが、100年もすれば誰もそんなもの気にも留めません。日常生活で100年前の一般人のこと思い出したり考えることってありますか?
私はありません。
太陽系のちっぽけな惑星の、何十億人といる有象無象のうちの一人の、長くてもたったの100年間なんて大したことないと思いませんか?
だから「生きる意味」なんて難しいこと考えずに嫌なことは嫌と言い、好きなことを目いっぱい楽しめば良いと思います。
歴史に名を遺すとか生きた証を残す必要なんてありますか?出来なくても何の問題もないですよ。
我慢ばかりだったけど歴史に名を遺す人生
歴史に名を遺せなかったけど好きなことを目いっぱい楽しんだ人生
私は後者の人生を歩みたいです。
「仕事」と「労働」と「作業」の違い
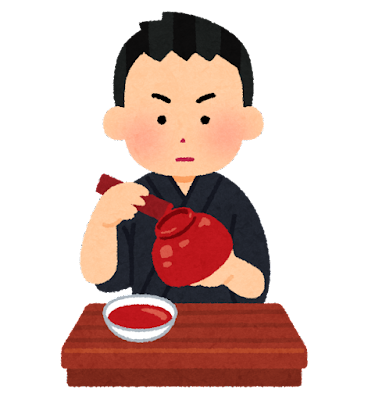
いつの間にか人々は、人間らしい「観照生活」を失ったのみならず、人間らしい「仕事」も失って<労働する動物>に成り下がり、歯車のような「労働」によって次々に消費財を生み出しては、取り憑かれたようにこれを消費するという、人間らしからぬ状態に陥ってしまったのです。
~中略~
つまり、私たちの現代とは、決してギリシャ時代よりも進歩したのではなく、皆が<労働する動物>という名の奴隷以下の存在に成り下がってしまい、人間らしい「観照」も「仕事」も見失ってしまった時代なのです。
「仕事なんか生きがいにするな」P.74,P.75より抜粋
*観照:本質を見極めること
ここでは「仕事」という言葉と「労働」という言葉が意図的に使い分けられていると思います。
私も同じように考えていて、「仕事」と「労働」と「作業」は全て以下のように区別しています。
| 働く時間 | 働く場所 | 業務量 | 給与 | スキルや知識 | 例 | |
| 仕事 | 自由 | 自由 | 自由 | 青天井 | とても必要 | 職人 |
| 労働 | 長い | 不自由 | 多い | 普通 | 必要 | サラリーマン |
| 作業 | シフト制 | 不自由 | 普通 | 少ない | 不要 | バイト・パート |
大学生のアルバイトが「仕事が忙しくてさ~」なんて言ってたらクスッとしちゃいますよね。
だってアルバイトはスキルや知識も必要ない「作業」なんですから。
同じように社会人でも自分がやっているのを「仕事」だと勘違いしている人が多いと思います。
あなたのそれは「労働」ではないですか?
残念ながら私も現状「労働者」です。
やりたくもないことを、何時間もバスと電車を乗り継いで会社まで行き、とんでもない業務量を夜遅くまで残業して何とかこなし、手取り30万もいかない・・・
早くこんな日々から逃れるため、コツコツ株式投資や副業を頑張ります!
夏目漱石と「超越的0人称」

「本当の自分」になる経験が起きると、必ずや一定期間の後に、「自分」への執着が消えるという新たな段階に入っていきます。
漱石も例外ではなく、「自己本位」の状態の後にこの段階が訪れます。その境地を漱石は「則天去私」という言葉で表しました。
これは彼の造語なのですが、「天に則り私を去る」という意味で、「自分」という「一人称」への執着が消えた「超越的0人称」の境地を表しているのです。
「仕事なんか生きがいにするな」P.101より抜粋
「衣食足りて礼節を知る」という言葉があるように、まず自分が満たされていないと他人へ施そうとは思えないという概念に通じるところがあると思います。
まず「本当の自分」を獲得する、すなわちやりたいことを実現することによって、やっと自分への執着が消えて誰かを幸せにしたいとかを考えることが出来るようになるのではないでしょうか?
若い時にやんちゃしていたような人が大人になったらそんじょそこらの人よりも立派になっていた、なんていうのも「本当の自分」を獲得し「超越的0人称」の境地に辿り着いた結果なのかもしれないですね。
過去の記事で私は結婚に向いているのは「自分を楽しませるのに飽きた人」ではないかと提唱しましたが、これは「本当の自分」になり「超越的0人称」の境地に辿り着いた人とも言えますね。
私は今は結婚したいとか思わないのですが、「超越的0人称」の境地に辿り着くことが出来れば結婚願望が出てくるかもしれません。
昨今の恋愛・結婚離れの原因も、多くの人が「本当の自分」になれていないからでは?
【参考】結婚を哲学する
将来に備えすぎ

「苦しいこと」「我慢すること」こそ正当なことで、「楽しむこと」「心地よいこと」は堕落だとして罪悪感を覚える。そういうメンタリティで窮屈な人生を送っている人は、今日でも少なくありません。
~中略~
生きることを謳歌し、美に生きることが「労働」よりも下らないこととして扱われてしまうのだとしたら、それは人間性の大いなる堕落であり、虫レベル、つまり「アリ」のメンタリティが人間の人間らしさを嘲笑しているという、実に由々しき事態なのではないかと思うのです。
~中略~
「今を生きること」をないがしろにしてまで将来に備えるのは、本末転倒以外の何物でもありません。
「仕事なんか生きがいにするな」P.183,P.184より抜粋
このページを読んで頭をよぎったのは「老後はどうするの?」という言葉です。
私個人の回答としては「安らかに眠ればいいじゃん」です。
頭は禿げて、目は老眼、耳は遠い、味も濃い味しか分からない、首は凝る、肩は上がらない、腰は痛い、膝は固まる・・・こんな状態になってからやりたいことって何でしょう?
こうなる前に全力で楽しんだ方が良いと思いませんか?
年を取るまで労働の日々を生き、上記のような状態になってからやっと自由になるなんて私はごめんです。
人生への準備には、もううんざりした。今こそ生きてみたいんだ。
サマセット・モーム
年金という制度も解せません。年を取ってからお金なんていらないから、今使わせて欲しいです。
しかも後の世代ほど払い損だし・・・
【参考】目次1.日本の年金制度と負担増
【参考】学習院大学 鈴木亘教授 世代間損得勘定(P.25)
https://www.taro.org/nenkinbenkyokai.pdf
まとめ
・子供の「嫌だ」という主張を受け入れてあげないと、主体性が育たない
・生きる意味なんて難しいこと考えずに、人生を楽しめば良いのでは?
・「労働」を止めて「仕事」をしよう!
・「本当の自分」を獲得することによって、やっと自分への執着が消えて誰かを幸せにしたいと考えることが出来るようになる
・老化する前にやりたいことを楽しもう!
以上、泉谷閑次の「仕事なんか生きがいにするな」の紹介でした。
気になった方はぜひ読んでみてください。